本学自己点検評価室では、本学の教育への理解を深めていただくことを目的として、下記のとおり公開授業を実施します。
前期:2023年7月3日(月)~7月7日(金)、7月13日(木)
後期:2023年11月27日(月)~12月1日(金)
「2023年度公開授業一覧」をご覧下さい。
在学生、保証人、卒業生、理事・監事、評議員及び非常勤教員を含む本学教職員、高等学校関係者、教育関係者(実習指導者)、受験生(受験予定者)
公開授業の参観を希望される方は、以下の方法にてお申し込みください。
①本学教職員・非常勤職員
→連絡用クラスルームにあるフォームにて申し込み受付
②佐保会学園理事・監事・評議員
→理事会で配布された申し込み用紙にて申し込み受付
③在学生、保証人、卒業生、高等学校関係者、教育関係者(実習指導者)、受験予定者
→こちらのフォームにて申し込み受付 〆切:2023年6月26日(月)
お申し込みされた授業の日時・講義室等は、メール返信にてご連絡いたします。
2、3日(土・日・祝を除く)経っても返信メールが届かない場合は、お手数ですが
お電話にてご連絡ください。
◆教材やプリント等の準備のため6月26日(月)17時までにお申し込み下さい。
◆6月26日以降に「公開授業参観案内」をメールにて返信いたします。
・事前に申し込みされた授業以外の参観はご遠慮ください。
原則として授業時間全体を参観いただき、途中入室や退室はしないでください。
・事前にメールにてお送りした「公開授業参観案内」をご一読ください。
・メールにて授業評価シートをお送りしますので、回答・返送のご協力をお願いいたします。
奈良佐保短期大学 自己点検評価室
〒630-8566 奈良市鹿野園町806
電話:0742-61-3858(代)
FAX:0742-61-8054
e-mailアドレス:tenke_n30@narasaho-c.ac.jp
2023年度の公開授業は、前期14科目・後期8科目の公開をしました。
今年度は、公開授業検討会及び公開授業報告会のテーマを「意欲的な受講態度の育成」とし、それぞれ授業でどのように取り組んでいるのか、またどのように授業を進めればよいか等を検討会(担当者と参観者で実施)で話合い、その内容を報告会で授業担当者から報告してもらいました。
■【2023年後期】
後期に参観された科目は、次の通り
「こども家庭支援論」「事業計画論」「こども家庭支援の心理学」「教育とICT活用」「生活科教育法」「国語表現法」「医療的ケアII」「栄養指導論実習I」
■【2023年前期】
前期に参観された科目は、次の通り
「音楽I」「こどもと環境II(指導法)」「乳児保育II」「マーケティング」「人権と差別」「図画工作」「基礎栄養学」「食品衛生学」「調理学実習III」「情報リテラシー」
2022年度の公開授業は、前期14科目・後期9科目を公開しました。
今年度は、公開授業検討会及び公開授業報告会のテーマを「事前・事後学修」とし、それぞれ授業でどのような事前・事後学修を実施しているか、どのような事前・事後学修が効果的であるか等を検討会(担当者と参観者で実施)で話合い、授業担当者より報告会で全体に報告してもらいました。
■【2022年度 後期】
後期は「こどもと環境I」「ゼミナールⅡ」「臨床栄養学」「生活支援技術Ⅱ」「家事支援の技法Ⅰ・被服」「国語表現法」「音楽Ⅱ」「情報処理演習Ⅰ」「ゼミナールⅡ」を公開しました。
■【2022年度 前期】
前期は「心理学」「図画工作」「栄養指導論Ⅰ」「奈良の伝統文化Ⅰ」「認知症の理解Ⅱ」「体育」「人権と差別」「社会的養護Ⅱ」「ゼミナールⅡ」「専門調理」「保育原理」「調理実習Ⅲ」「基礎栄養学」「こどもの理解と援助」を公開しました。
2021年度の公開授業は、より多くの教職員に参観してもらうため前期10科目・後期11科目を公開しました。
また、昨年度まで実施していた検討会は公開授業から日程があいてしまっており、検討会というよりも公開授業の報告会となってしまっているという意見を受け、今年度より公開授業終了後1週間以内に授業担当者及び参観者で検討会を行い、その後 課題等の共有する場として公開授業報告会を実施しました。
■【2021年度 後期】

後期は「こどもと健康Ⅰ」「栄養指導論実習Ⅰ」「社会的養護Ⅰ」「事業計画論」「国語表現法」「社会調査法」「医療的ケアⅡ」「算数科教育法」「経営学総論」「保育教育相談支援」「食品材料学」を公開しました。
■【2021年度 前期】


前期は「障害の理解Ⅰ」「こども家庭支援の心理学」「栄養指導論実習Ⅱ」「道徳教育の理論と方法」「保育表現演習Ⅰ」「乳児保育Ⅰ」「調理実習Ⅲ」「社会福祉概論」「基礎栄養学」「介護の基本Ⅰ」を公開しました。
2020年度の公開授業は、「ルーブリック評価」をテーマに前期3科目・後期2科目で実施しました。
公開授業検討会では、授業担当者からそれぞれの授業概要の説明や評価をどのように実施しているかの発表があり、参加した教職員とも今後の授業の課題等の意見交換が行われました。
■【2020年度 後期】


後期は「保育内容(人間関係)」「生活支援技術Ⅱ」を公開しました。
■【2020年度 前期】

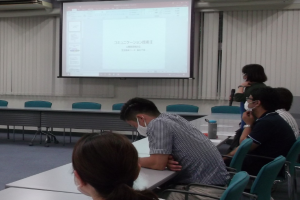
前期は「奈良の食と文化」「社会保障」「コミュニケーション技術Ⅱ」を公開しました。
2019年度の公開授業は、「アクティブラーニング」をテーマに前期3科目・後期3科目で実施しました。
また、公開授業検討会では昨年と同様に公開授業を実施した講義だけを振り返るのではなく、授業担当者からそれぞれの授業概要の説明、アクティブラーニングをどのように取り入れているかについて報告、意見交換を行いました。
■【2019年度 後期】


後期は「社会調査法」「音楽科教育法」「体育科教育法」を公開しました。
■【2019年度 前期】


前期は「栄養指導論実習Ⅱ」「教育原理)」「数の世界」を公開しました。
2018年度の公開授業はテーマを「実習と実習評価」とし、各学科・コースの学外実習やインターンシップに関連する授業を選択して実施しました。
■【2018年度 後期】

後期は「保育実習指導Ⅱ」「ゼミナールⅡ(食物栄養)」「保育実習指導Ⅰa」を公開しました。
■【2018年度 前期】
前期は「介護総合演習Ⅰ」「ゼミナールⅠ(ビジネスキャリア)」「教育実習指導b」を公開しました。
■【2017年度後期】
後期はこれまで公開授業を行ったことのない教員を対象に、「保育(人間関係)」「医療的ケアⅠ」「栄養指導論実習Ⅰ」「食料経済」を公開しました。
次年度より参観時に使用している評価シートを見直すことを目的に、他大学で使用している項目を参考に新たな評価シートを用いました。検討会での参観者からの意見を基に、今後の授業改善に活かせるよう、引き続きFD委員会を中心に検討を進める予定です。

■【2017年度 前期】
6月26に「社会学」6月27日「食品衛生学実習」7月3日「生活リクリエーション」7月4日「保育(健康)」の講義、演習、実習など形態の異なる4科目を公開対象としました。また、2016年度より参観対象者を学生、保証、卒業生、理事、監事、評議員にまで広げましたが、今回評議員が参観され、貴重なご意見をいただくことができました。

■【2016年度 後期】
後期は、これまで公開授業を行ったことのない教員を対象に、「医療的ケアⅠ」「保育心理学演習」「教育方法の理論と実践」の3科目を公開対象として、11月18日、11月22日の2日間実施しました。11月22日に行った公開授業検討会では、担当教員からの授業改善のための問いかけに、参加者が意見を述べるなど、意見交換が行われました。

■【2016年度 前期】
今年度も昨年度同様、各教員の参観希望実施日を選んで公開授業を行いました。対象範囲も非常勤教員を含む本学教職員、学生、保証人、卒業生、理事、監事、評議員に公開することを周知しました。演習授業を中心に、「音楽基礎演習Ⅰ」「数の世界」「生活支援技術Ⅰ」「調理実習Ⅲ」の4科目を対象に実施しました。講義形式では見られない学生の姿を見ることができ、公開授業検討会でも演習授業ならではの悩みやそれに対する意見交換があり、貴重な場となりました。

■【2015年度 後期】
前期と同様に、各教員の参観希望実施日を選んで、4科目の公開授業を行いました。11月9日「経営学総論」・12月1日「保育(表現・幼児造形)」・12月2日「国語表現法」・12月25日「体育科教育法」の公開授業及び、公開授業検討会を行いました。参加者は、延べ27名でした。各検討会では、教員が、参観者に授業運営に対する意見を求めながら、今後の授業に生かしていける方法等が話し合われました。
■【2015年度 前期】
今年度は各教員の参観希望実施日を選んで、公開授業を行いました。また、公開授業の対象範囲を広げ、これまで非常勤教員を含む本学教職員としていたものに加えて、学生、保証人、卒業生、理事、監事、評議員に公開することを周知しました。5月25日・5月26日・5月27日・5月28日の4日間、5科目を対象に実施しました。また公開授業検討会も併せて実施しました。参加者は延べ25名でした。 各検討会では学生の実態を踏まえながらより良い授業を行うための活発な意見交換が行われました。

■【2014年度 後期】
10月27日、29日、30日に「基礎ゼミナールⅡ」、10月28日に「家庭支援論」を対象科目として実施しました。13科目全体で延べ52名の参観がありました。今回は複数開講の「基礎ゼミナールⅡ」を公開対象としたため、公開授業検討会を実施日ではなく、10月30日(木)のFD研修会後に開催しました。各学科・コースの「基礎ゼミナールⅡ」の実施内容や問題点の共有、「家庭支援論」で実施されたMSF(ミッドターン・スチューデント・フィードバック)についての検討を行いました。

■【2014年度 前期】
5月12日に「応用栄養学」「文字とことばの歴史」、5月16日に「認知症の理解Ⅱ」「相談援助演習Ⅰ」を対象科目として実施しました。4科目全体で延べ33名の参観がありました。併せて当日の5時限に、公開授業検討会を開催しました。

■【2013年度 後期】
10月7日に「介護概論Ⅱ」「音楽Ⅱ」、10月11日に「保育実習指導Ⅱ」「情報処理演習Ⅱ」を対象科目として実施しました。4科目全体で延べ36名の参観がありました。併せて10月7日分を翌8日、10月11日については当日の5時限に公開授業検討会を開催しました。 興味を持たせる工夫として、「実習先の状況を学生自身が振り返りながら進めていた」、「曲の背景やその曲が持つ意味を各自で調べさせたり、歌詞の内容について(教員から)質問して答えさせたりするなど、常に考えている状態にしていた」などが挙げられました。 改善に向けては、「出席の点呼中に前回の課題をさせるとよい」、「グループディスカッションのテーマごとに各グループの意見を発表させると、より共有が進みグループの議論にフィードバックできる」という意見が出されました。

■【2013年度 前期】
5月13日に「保育者論」「障害の理解Ⅰ」「数の世界」、5月15日に「介護過程Ⅰ」「保育(健康)」を対象科目として実施しました。5科目全体で延べ36名の参観がありました。併せて当日の5時限に、公開授業検討会を開催しました。 興味を持たせる工夫として、「身近な例を取り上げることで学生に自分で考えさせる」、「すぐに答えを提示せず、じっくり考えさせる機会を与えていた」、「教員の体験等を取り入れることで、学生が真剣に聞いていた」などが挙げられました。 改善に向けては、「発言しやすい雰囲気を作る。グル—プディスカッションを取り入れる」、「学生に発言の機会を与え、質問を投げかける」という意見が出されました。

■【2012年度 後期】
2012年度は公開授業日を2日間とし、5科目を参観科目として設定しました。 公開授業検討会を授業当日の16時20分から3号館会議室で開催し、5月14日は21名、18日は18名の出席がありました。 授業検討会では、参観授業ごとのグループに分かれて、参観した授業の評価できる点やさらなる改善策について、意見を交換しました。

■【2012年度 前期】
後期は、参観科目を各日2科目にしぼり、公開授業検討会を授業当日に開催しました。10月8日は14名、12日は13名の出席がありました。授業検討会では、参観した授業についての意見を交換し、学生指導などにも話題が広がりました。

■【2011年度 後期】
前期の第8回FD研修会をふまえ、FD推進委員会から具体的な授業改善のための取組について、7つの提言をしました。 その中から、後期授業で1つ以上取り入れて改善を図ることを依頼し、期末にはその効果についてアンケート調査を行いました。
■【2011年度 前期】
第8回FD研修会では、公開授業 評価シートから見えてくるものについて、3つのテーマと観点に分かれてグループ討議を行いました。 その議論をふまえて、FD推進委員会から全科目が実施可能な具体的な提言を行い、後期授業において実施することとしました。
■【2010年度 後期】
2010年度後期の公開授業検討会を、11月4日(木)13時30分から15時まで3号館会議室で開催しました。 24名の出席があり、3つのテーブルに分れて「参観した授業の評価できる点」「あきさせないための工夫」について意見を交換しました。




■【2010年度 前期】
2010年度前期の公開授業検討会を、6月3日(木)13時30分から15時まで3号館会議室で開催しました。 38名の出席があり、「授業改善の方法を検討する」をテーマに7つ観点別のテーブルに分れてについて概要と提言について意見を交換しました。
■【2009年度 後期】
2009年度後期の公開授業検討会を、12月28日(月) 15時から16時30分まで3号館会議室で開催しました。 36名の出席があり、「実施された公開授業について、授業改善の方途を検討する」をテーマに意見を交換しました。

